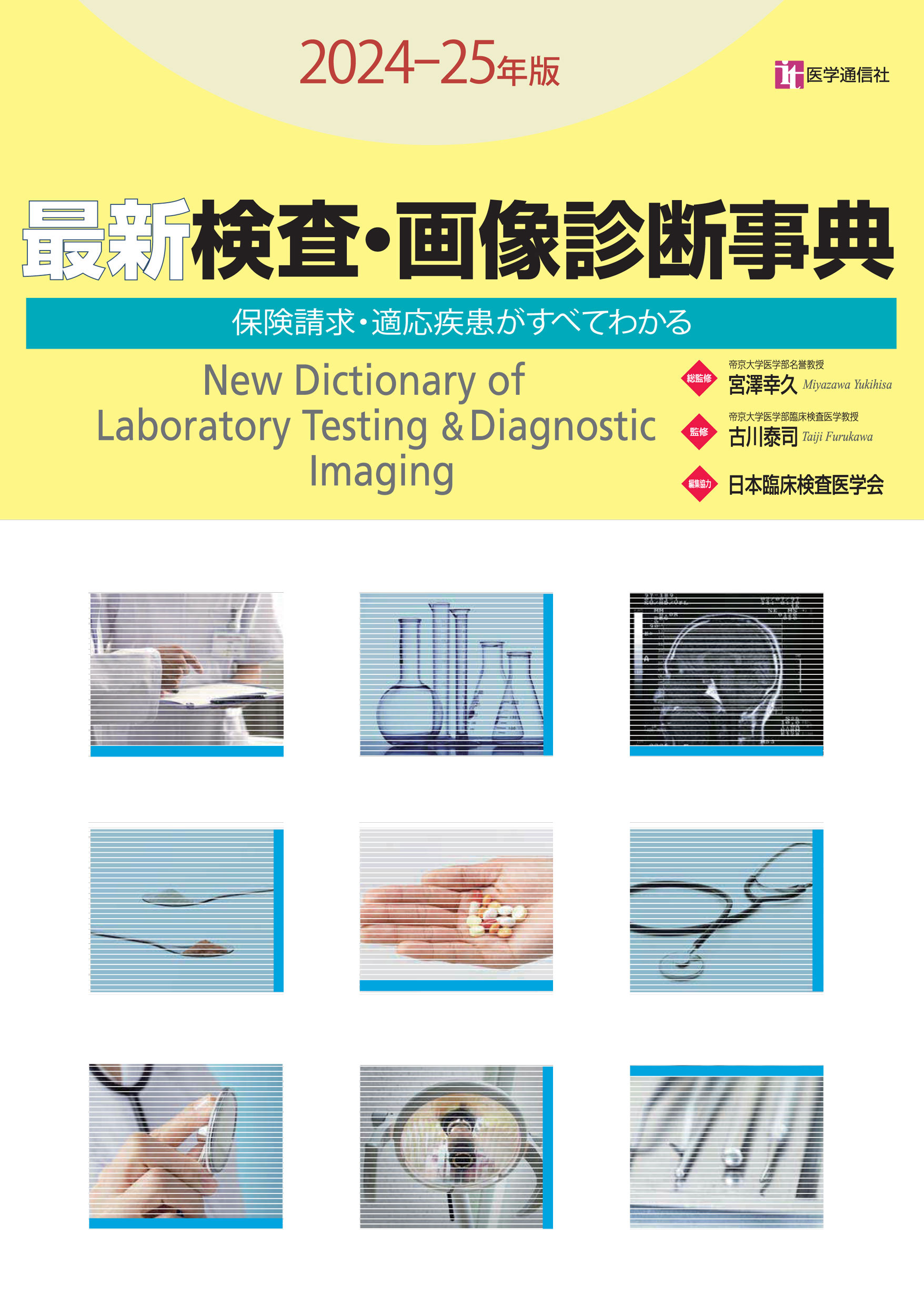『弊社は検査機器・試薬メーカーでありまして、検査を受託することが出来ません。弊社プライマリケアサイトのスピード検索におきましては、 株式会社 医学通信社からの許諾を受けて「最新検査・画像診断事典」の情報を一部転載させていただいております。』
第5章 免疫学的検査
項目名称
寒冷凝集反応
目的
低温(4℃)で赤血球を凝集する抗体である寒冷凝集素(cold agglutinin; CA)を検出する検査である。CAは原因不明の寒冷凝集素症や寒冷型自己免疫性溶血性貧血のほか,感染症(マイコプラズマ,ウイルス)や免疫グロブリン異常を呈する病態で出現する。
方法・保険請求のポイント
| 方法 | 赤血球凝集法(HA) |
|---|---|
| 検体検査実施料 |
11点 |
| 保険請求 | |
|
■本区分の10から16まで,18,19,23および37に掲げる検査を2項目または3項目以上行った場合は,所定点数にかかわらず,それぞれ320点または490点を算定する。 |
|
| D000~D024に係る共通事項 | |
|
■検体検査の費用は,第1款(検体検査実施料)および第2款(検体検査判断料)の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ■入院中の患者以外の患者について,緊急のために,保険医療機関が表示する診療時間以外の時間,休日または深夜において,当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は,時間外緊急院内検査加算として,第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし,この場合において,同一日に第3号の加算は別に算定できない。 ■特定機能病院である保険医療機関においては,入院中の患者に係る検体検査実施料は,基本的検体検査実施料に掲げる所定点数および当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。 ■入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって,別に厚生労働大臣が定めるものの結果について,検査実施日のうちに説明したうえで文書により情報を提供し,当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に,5項目を限度として,外来迅速検体検査加算として,第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。 時間外緊急院内検査加算 ★時間外緊急院内検査加算については,保険医療機関において,当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間,休日または深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際,医師が緊急に検体検査の必要性を認め,当該保険医療機関において,当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。 なお,当該加算の算定に当たっては,当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。 ★検査の開始時間が診療時間以外の時間,休日または深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお,時間外等の定義については,A000初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様である。 ★同一患者に対して,同一日に2回以上,時間外,休日または深夜の診療を行い,その都度緊急の検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む)も,1日につき1回のみ算定する。 ★現に入院中の患者については算定できない。ただし,時間外,休日または深夜に外来を受診した患者に対し,検体検査の結果,入院の必要性を認めて,引き続き入院となった場合は,この限りではない。 ★時間外緊急院内検査加算を算定する場合においては,A000初診料の注9およびA001再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。 ★緊急の場合とは,直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について,通常の診察のみでは的確な診断が困難であり,かつ,通常の検査体制が整うまで検査の実施を見合わせることができないような場合をいう。 外来迅速検体検査加算 ★外来迅速検体検査加算については,当日当該保険医療機関で行われた検体検査について,当日中に結果を説明したうえで文書により情報を提供し,結果に基づく診療が行われた場合に,5項目を限度として,検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。 ★以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には,その規定にかかわらず,実施した検査項目数に相当する点数を加算する。 D006出血・凝固検査の「注」の場合 D007血液化学検査の「注」の場合 D008内分泌学的検査の「注」の場合 D009腫瘍マーカーの「注2」の場合 例 患者から1回に採取した血液等を用いてD009腫瘍マーカーの「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合,検体検査実施料の請求はD009腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが,外来迅速検体検査加算は,行った検査項目数が2項目であることから,20点を加算する。 ★同一患者に対して,同一日に2回以上,その都度迅速に検体検査を行った場合も,1日につき5項目を限度に算定する。 ★A002外来診療料に含まれる検体検査とそれ以外の検体検査の双方について加算する場合も,併せて5項目を限度とする。 ★現に入院中の患者については算定できない。ただし,外来を受診した患者に対し,迅速に実施した検体検査の結果,入院の必要性を認めて,引き続き入院となった場合は,この限りでない。 【レセプト摘要欄】 〈時間外緊急院内検査加算〉検査開始日時を記載する。 (引き続き入院した場合)引き続き入院した場合である旨を記載する。 〈外来迅速検体検査加算〉(外来診療料を算定した場合であって,当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合)当該加算を算定した日に行った検体検査の項目名を記載する。 (引き続き入院した場合)引き続き入院した場合である旨を記載する。 |
|
■:告示、★:保医発通知
検体検査判断料
令和6年度診療報酬改定に基づきます。
| 判断料 |
|---|
| 免疫学的検査判断料144点 |
| 算定条件 |
|
注 1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。 2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞ふん便等検査判断料は算定しない。 3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-30までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。 4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。 イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点 ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点 ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点 ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。 9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。 (1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。 (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。 (3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。 (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。 (5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。 (6) 区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査から区分番号「D006-9」WT1 mRNAま で、区分番号「D006-11」FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査まで及び区分番号「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から区分番号「D006-28」Y染色体微小欠失検査までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。 (7) 「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。 (8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。 (9) 「注6」に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」のうち、マイクロサテライト不安定性検査(リンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る。)、区分番号「D006-4」遺伝学的検査、区分番号、「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査又は区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査を実施する際、以下のいずれも満たした場合に算定できる。 ア 当該検査の実施前に、患者又はその家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行っていること。 イ 患者又はその家族等に対し、当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行っていること。 なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査を実施する際、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合の当該区分に係る診療報酬の請求は、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。その際、遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、遺伝カウンセリング加算を算定する患者については、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「23」がん患者指導管理料の「ニ」の所定点数は算定できない。 (10) 難病に関する検査(区分番号「D006-4」に掲げる遺伝学的検査及び区分番号「D006-20」に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。)に係る遺伝カウンセリングについては、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた他の保険医療機関の医師と連携した遺伝カウンセリング(以下「遠隔連携遺伝カウンセリング」という。)を行っても差し支えない。なお、遠隔連携遺伝カウンセリングを行う場合の遺伝カウンセリング加算は、以下のいずれも満たす場合に算定できる。 ア 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、疑われる疾患に関する十分な知識等を有する他の保険医療機関の医師と連携し、遠隔連携遺伝カウンセリングの実施前に、当該他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行うこと。 イ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。 ウ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。 エ 当該他の保険医療機関は本区分の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。 オ 当該他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行うこと。また、個人の遺伝情報を適切に扱う観点から、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。 カ 事前の診療情報提供については、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。 キ 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。 (11) 「注7」に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を実施する 際、(9)のア及びイのいずれも満たした場合に算定できる。なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査 診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。 (12) 「注8」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。 (13) 「注9」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。 |