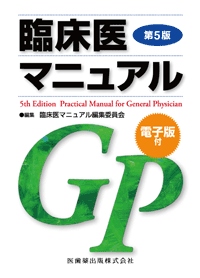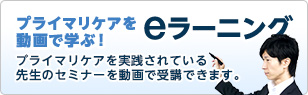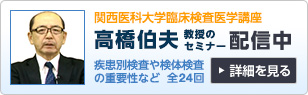疾患スピード検索で表示している情報は、以下の書籍に基づきます。
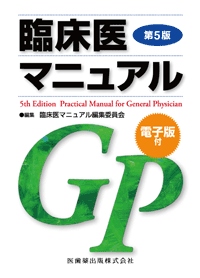
「臨床医マニュアル 第5版」は、医歯薬出版株式会社から許諾を受けて、書籍版より一部(各疾患「Clinical Chart」および「臨床検査に関する1項目」)を抜粋のうえ当社が転載しているものです。転載情報の著作権は,他に出典の明示があるものを除き,医歯薬出版株式会社に帰属します。
「臨床医マニュアル 第5版」 編集:臨床医マニュアル編集委員会
Copyright:(c) Ishiyaku Publishers, Inc., 2016.
詳細な情報は「臨床医マニュアル第5版」でご確認ください。
(リンク先:http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.aspx?bookcode=731690)
Clinical Chart
- 昔は日本でも流行し死亡率が高かったコレラ,腸チフス,赤痢などの各種感染症は,医療水準の向上,生活水準の向上,上・下水道の整備など公衆衛生状態の改善により患者数が激減し,発展途上国で感染して帰国後発症するか,あるいは輸入食品により感染するというケースが多くなった.
- 航空機の利用による国際交流の進展,海外渡航者の増加に伴い,日本ではほとんど見られなくなった上記のような疾患や,本来日本には存在しない感染症が海外から持ち込まれることが多くなり,輸入感染症とよばれている.
- 「輸入感染症」という用語は行政用語としてまず使われ,今日医学界でも使用されているが,明確な定義は存在しない.
- これらの疾患は一般の医療では遭遇する機会が極めて少ないため,医療従事者の側に経験や知識が乏しく,診断が困難である.初期治療が不適切になり予後を悪化させたり,適切な感染対策がとれずに集団感染が発生したりする危険性がある.診断のつかない発熱疾患の診療の際には,海外渡航歴も確認する必要がある.
- 今日の日本では頻度的に低いといっても国際的な視野に立てば,マラリアなど年間の総罹患者数,死亡者数などが圧倒的に多い感染症が含まれている.
- 日本では明治 30 年(1897 年)に制定された法律に基づいて法定伝染病が指定され,隔離などの対応が実施されていた.有効な治療薬(抗菌薬など)が多数使用可能な現代では,法定伝染病は診断さえつけば簡単に治療できる疾患が多くなり,実情にそぐわなくなっていた.大幅な法の改訂が実施されて 1999年4月に「感染症新法」が制定され,2003 年 11月,2013 年 3 月に一部改正され,名称は「感染症法」になった.
- 病原性の強い各種病原体を生物化学兵器として使用するテロリズムの発生が危惧されており,2001 年には実際に米国で炭疽菌が使用され,痘瘡(天然痘)やペストなども使用される可能性が指摘されている.
- この項目では届け出が必要な感染症や輸入感染症について一般の医者が最低限知っているべき基本的な事項について説明する.
感染症の分類
①1 類感染症 感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症.②2 類感染症 感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症.③3 類感染症 感染力,罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が高くはないが,特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症.④4 類感染症 ヒトからヒトへの感染はほとんどないが,動物,飲食物などの物件を介してヒトに感染し,国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症.⑤5 類感染症 国が感染症発生動向調査を行い,その結果に基づき必要な情報を国民や医療関係者などに提供・公開していくことによって,発生・拡大を防止すべき感染症⑥指定感染症 1~3 類および新型インフルエンザ等感染症に分類されない既知の感染症のなかで,1~3 類に準じた対応の必要が生じた感染症(政令で指定,1 年限定)⑦新感染症 ヒトからヒトに伝搬すると認められる感染症で,既知の感染症と症状などが明らかに異なり,その伝搬力および罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症(当初は都道府県知事が厚生労働大臣の技術的指導・助言を得て個別に応急対応する,政令指定後は1 類感染症に準じた対応を行う).⑧新型インフルエンザ等感染症(新型/再興型インフルエンザ) 新たにヒトからヒトに伝染する能力を有することとなったインフルエンザや,かつて世界的規模で流行したインフルエンザでその後流行することなく長期間が経過しているもので,一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから,当該感染症の全行的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの.
<具体的分類>
①1 類感染症 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡(天然痘).南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱②2 類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ),コレラ,結核,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(severe acute respiratory syndrome:SARS,病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスによるものに限る),鳥インフルエンザ(H5N1)③3 類感染症 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症.腸チフス,パラチフス④4 類感染症 E 型肝炎,ウエストナイル熱,A 型肝炎,エキノコックス症,黄熱,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,Q 熱,狂犬病,コクシジオイデス症,サル痘,重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る),腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,炭疽,チクングニア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,鳥インフルエンザ(H5N1 およびH7N9 を除く),ニパウイルス感染症,日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,B ウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウイルス感染症,発疹チフス,ボツリヌス症,マラリア,野兎病,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピラ症.ロッキー山紅斑熱⑤5 類感染症- ①すべての医療機関が届け出る疾患:アメーバ赤痢,ウイルス性肝炎(E 型肝炎およびA 型肝炎を除く),急性脳炎(ウエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く),クリプトスポリジウム症,Creutzfeldt-Jakob 病,劇症型溶血性レンサ球菌感染症,後天性免疫不全症候群,ジアルジア症,侵襲性インフルエンザ菌感染症,侵襲性髄膜炎菌感染症,侵襲性肺炎球菌感染症,髄膜炎菌性髄膜炎,先天性風疹症候群,梅毒,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,風疹,麻疹
- ②指定された医療機関(小児科定点)が届け出る疾患:RS ウイルス感染症,咽頭結膜熱,A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎,感染性胃腸炎,水痘,手足口病,伝染性紅斑,突発性発疹,百日咳,ヘルパンギーナ,流行性耳下腺炎
- ③指定された医療機関(基幹定点)が届け出る疾患:クラミジア肺炎(オウム病を除く),細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎は除く),マイコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る),ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症,薬剤耐性アシネトバクター感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症
- ④指定された医療機関(眼科定点)が届け出る疾患:急性出血性結膜炎,流行性角結膜炎
- ⑤指定された医療機関(インフルエンザ定点)が届け出る疾患:インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)
- ⑥指定された医療機関(性行為感染症定点)が届け出る疾患:性器クラミジア感染症,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コンジローマ,淋菌感染症
⑥指定感染症 既知の感染症のなかで1~5 類に準じた対応の必要が生じた感染症.2006 年4 月,H5N1 の高病原性鳥インフルエンザが指定感染症に指定され,2013 年5月には感染拡大が続いているH7N9 型鳥インフルエンザが指定感染症に指定された.1~2 年の期限つきだが,感染者の健康診断勧告,強制入院,就業制限などが可能となる.⑦新感染症 1類感染症と同様の扱いを必要とする未知の感染症.⑧食中毒 1997 年5 月に食品衛生法が改正され,食中毒病因物質に「小型球形ウイルス(small round structured virus:SRSV)」と「その他のウイルス」が追加された.2003 年8 月に「SRSV」が「ノロウイルス」に変わり,ノロウイルス以外のSRSV は「その他のウイルス」に分類されるようになった.なお食品衛生法に基づき,食中毒患者を診断した医師は,24 時間以内に保健所に届け出る必要がある.なお食中毒の原因物質は細菌(感染型:カンピロバクター,サルモネラ,腸管出血性大腸菌,毒素型:黄色ブドウ球菌,ボツリヌスなど),ウイルス(ノロウイルスなど),寄生虫(アニサキスなど),自然毒(フグ毒,貝毒,毒キノコなど),化学物質(重金属,農薬など)などさまざまであるが,事件数および患者数はウイルス性と細菌性が多い.食品衛生法における食中毒の定義は「食品,添加物,器具もしくは容器包装に起因して中毒した患者もしくはその疑いのある者」であり,感染症新法では「病因物質の種別に関わらず,飲食に起因する健康障害は食中毒として取り扱う」としている.